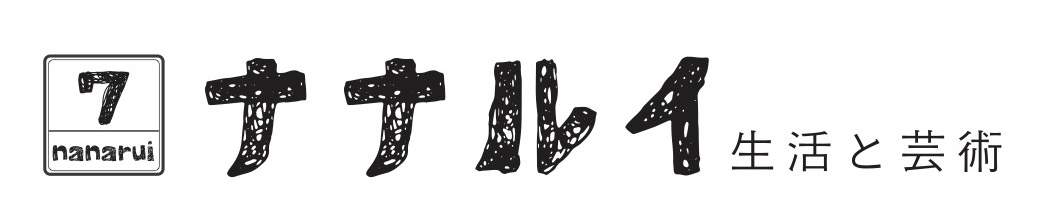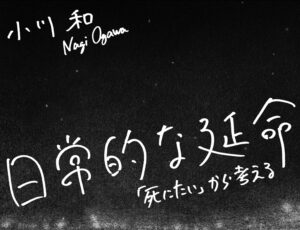『日常的な延命』評④ 佐藤述人
『日常的な延命』について、作家の佐藤述人さんに書評を寄せていただきました
作家 佐藤述人
アクチュアルな態度で
無力をばれたくない。無能をばれたくない。なるべく声をひそめて注目されないよう努めたい。注目を浴びたら、それだけ自分の足りなさや異質さがばれるリスクが高まるからだ。なるべく広いところを避けて明るみに出ないよう努めたい。明るみに出されたら、それだけ自分の愚かさや歪さがばれるリスクが高まるからだ。これは同時に、試されたくない、ジャッジされたくないという願望でもある。例えば自信のない分野についての何らかの試験を受けたくないと言うとき、これはたんに出来の悪い試験結果そのものを恐れてそう言う場合もあるにはあろうが、でもそれ以上に、出来の悪い結果が数字や成績として具体的に表れることで、いわば不出来の度合いが明文化され、その分野の自分の苦手さ(足りなさ/愚かさ)がばれるのを避けたいためにそう言う場合も想定できるだろう。試されてジャッジされることは自分の無力や無能が明るみに出されることでもあり、そうなればそこへの注目にも目隠しができなくなるはずだ。
人々に無力や無能がばれれば失望されるだろう。まず望むのはだれからも失望されない安全地帯に居続けることだ。でもそれはなかなか難しい。難しいが、それでもなお評価の失墜をきらうのなら、そのために初めから評価を受けたり期待されたりすること自体を避けるようになるだろう、もっと言えば評価を受けたり期待されたりする可能性の生じる場面に接近することからさえできるだけ距離をとって生活したい、そういう願望へも通ずるだろう。僕は小川和の言う〈安心欲求〉をまずは以上のようなものと解している。小川は「安心への願望」を「自身の言動が許されている状態であろうとする指向」(p.48)としている。また別のところでは、安心欲求を抱えた者について「自分を潜在的な危険のもとへ開くこと自体が難しく、承認欲求の回路に飲み込まれること自体にも抵抗を覚える」(p.103)と語っている。
ところでいま安心欲求に対するかたちで承認欲求という言葉が用いられた。これは当然のことで、というのもじつは本書において安心欲求なる表現は「本来承認欲求と安心欲求という2種類の意味合いに分けられるべきものが「承認欲求」というひとつの言葉の中へと吸収されてしまっているのではないか」(p.55、原文では傍点)との仮説のもと登場するのだったのだ。小川はもっと注意深く論じているが、注意力散漫な僕が乱暴に口走るのを許していただけるならば、承認欲求とは期待/失望の可能性へ飛び込むことを厭わずに明るみへと開かれて注目を浴びるのを望む欲求だと言っていいだろうか。だとすれば、実際に安心欲求が承認欲求の一部として語られている現状があるのなら、真逆の欲求がひとつの名で示されているという、端的にこれは不正確な状況だと言われねばならないだろう。にもかかわらずしかし、「承認欲求という言葉の強度によって安心欲求は覆い隠されてしまう」(p.308)あるいは「安心欲求を求めているのに、「承認欲求」という言葉が目前に立ちふさがり、それに頼るしかなくなるがために、うまく安心欲求にアプローチすることができない」(p.56)という事態の出来がいかにもあり得る話だと、これは生活実感として僕にもそう思われてならない。
その意味で、安心欲求というものを言語化して承認欲求から切り離して提示してみせただけでも本書の働きはすでに大きく、ゆえに広く読まれねばならないわけだが、表題や巻頭に載せられた短文からもわかるように小川はそもそも本書を〈日常的な延命〉について〈死にたい〉という気持ち(あるいは漏れた呟きとでも言ったほうが正確かもしれない)との対峙を通して考えるものと位置付けているのだった。「日常的な延命、まずそれは「死にたい」から考えることで始まる。「死にたい」から、どうにか生きるために考えたい。「死にたい」を起点にして、生きる方法を考えたい」(p.308)と彼は書いている。
では、安心欲求が承認欲求に隠されてしまうこの時代における「死にたい」を、彼はいかなるものと考えているのか。「理由が辿れる「死にたい」と、なんだかわからないけどやってくる幽霊的「死にたい」の「重ね合わせ」が作り出す状態。それこそが現代の「死にたい」なのではないか」(p.209)と小川は言う。が、その話をする前にまず「幽霊的「死にたい」を考える上での足場としたい」(p.210)とのちに言われることとなる〈バーチャルな主体〉についての議論に触れておかねばならない。
多量かつ極めて解像度の高い情報群に休みなく刺激され続けながら、またあらゆる価値を相対化できてしまう現代において、僕らはなかなか選択をしたり判断をしたりすることができない。ある選択の判断は別の選択方法によって相対化され得るだろうし、では先にその選択方法についての判断にけりをつけておこうとすれば、それすら更に別の選択方法に相対化されるだろう(そしてこの遡行は無際限に続く)。このような「相対化のブラックホール」(p.170)を想定しながら、「「相対化のブラックホール」と極めて相性の良いもの」(p.172)としてバーチャルな主体なるものは持ちだされる。「「バーチャルな主体」はとめどない相対化を促進する」(p.172)のだと小川は言う。あるいは同じ文脈の延長で「「バーチャルな主体」は、時間性のない主体」(p.172)だとも言われる。まとめて説明されている箇所を引用してみようか。
おそらく、過剰な情報処理に慣れるとその主体は、非常にバーチャルでなめらかなものになるのだ。テレビの画素数のように、でこぼこした穴が情報の密度で埋められれば埋められるほど、なめらかになる。情報のピクセルは、そのなめらかな世界の中で瞬時に飛び回り、時間という距離を感じさせなくなる。情報が「密に詰まりすぎていて、ゆえに軽い」というそのイメージ。現代を生きる人々もまた、デジタル環境の発展とともに、よりデジタルな情報処理に適した在り方へと変容してきている。(p.171、太字は原文では傍点)
ちょうどさっきこの原稿を書くのをさぼってVTuberの配信を見ていたら、視聴者から別の衣装のすがたが見たいとの要望がコメントされ、それに応えるかたちで配信画面上の彼女(というのはVTuberのことだ)の衣装が変更される場面にでくわした。重要なのは、その衣装チェンジが瞬時に、つまり時間性の欠如したかたちでおこなわれた点だ。VTuberの身体は文字通りバーチャルなものなわけで、この何気ない場面からも、バーチャルな主体の時間性のなさの一端が理解されよう。あるいは、VTuberは多くの場合において画面上のバーチャルな身体とパラレルに生身の身体があることにこそ意味があるのだと言われるならば、テレビゲームのキャラメイクを考えてみてもいい(僕はMiiを想像して書いているが何を例としてもほとんど同じように説明されよう)。任意のボタンを押せば顔の造りも体型も髪の長さも瞬時に変化する。また一定の数値にレベルアップしたら容姿の変化するキャラクターのことを考えてみてもいいかもしれない。19という数値に1が加わるだけで瞬時にがらりとコイキングはギャラドスという似てすらいない身体へ変化する。もしいま僕の手元にバーチャルな紅茶があって、それにバーチャルな角砂糖を入れたなら、おそらく瞬時に、コイキングがギャラドスになるのと同じ時間性のなさにおいて、あるいは19に1を足したら20になるのと同じ時間性のなさにおいて味が変化することだろう。しかし実際にはバーチャルな紅茶ではなくアクチュアルな紅茶しかない。この紅茶が甘くなるには角砂糖が溶けるのを待たねばならない。アクチュアルな紅茶の味には、角砂糖が溶けるまでの時間、切り離せないものとしてこの時間性も含まれているのだ。
いま僕は特に断りなくバーチャルに対置するかたちでアクチュアルという言葉を用いたが、これは実際、「いかにして「バーチャルな主体」を「アクチュアルな主体」にできるか、相対化の波を遅らせ、メッセージの一回性を深く享受できるようにするか」(p.200)と小川が模索しているからなのだった。「「バーチャルな主体」を抱えてしまう状態では多動的過ぎる自らを制御することが難しい。それをもっと落ち着かせて、地に足のついた状態に変えていくこと。決まり切った情報の渦から発生するコミュニケーションではなく、現在の出来事をひとつひとつ新鮮に受け止め、吟味できるような回路を手に入れること。こうした意味合いにおいて、アクチュアルという語をバーチャルに対置させている」(p.175)のだと言う。そのようにして彼は筋トレを例に挙げるだろう。
当たり前ではあるが筋トレによる体型の変化はMiiのキャラメイクのようにはいかない。そこにはどこまでもアクチュアルに時間性と個人差と好みが付きまとう。そして個人差や好みといったそれでしかないような手応えが、幅のある時間性のなかでこうなってしまったのだといったあんばいに形成されるとき、僕らはアクチュアルな重さを取り戻すことができるのではないか。かなりごく簡単に纏めてしまったが小川の筋トレ論の結論の要点はおおもねこのようなものだ。むろんこれは逆から読めば、筋トレとは違って大量のパターンの身体のどのかたちへでも瞬時に変化できる、そのような情報量の多さゆえの軽さにおいては、「自らが主体的に関わっていない情報を他者から大量に与えられ続けた結果、地に足をつけられるような重さの感覚が失われてしまう。軽すぎて動くことができなくなる」(p.203)といった具合に僕らが、相対化のブラックホールのなかで明晰に呆けることしかできなくなるだろうことの説明の強化にもなろう。僕はこれを考えるとき、少ない小銭を持って近所の駄菓子屋へ行っていた小学生のころには迷いなく商品の購入ができたのに、いまAmazonで飲食物を買おうとすると比較可能な情報の多さから何も選べなくなってしまう自分を顧みもした。ともあれバーチャルな主体とは、言ってしまえば、いかようにも相対化され得る軽さのゆえにこそ身動きのとれない主体のことなのだと理解して差し支えないだろう。
ここにいたって僕は幽霊的「死にたい」の話題へ帰ることができる。「「なんだかわからないが死にたくなる」とでも形容できるような「死にたい」」(p.208)を小川は「目の前に見えるようでありながら同時に見えないものでもあるとでもいった両義性」つまり「そこにないようにも思えるが、実感だけはある」(p.209)というニュアンスを込めて幽霊的「死にたい」と呼称しているのだという。
小川は現代を生きる僕らの置かれた現状について、個人情報が細かく分析されることで分類可能にされつつあることを踏まえたうえで、これを「生のすべてが統計的な予測の対象となってしまうようなアルゴリズムの時代」(p.210)とし、そのなかで人々には「自分の欲望や能力にはそれほど固有のものなどなく、世界は自分と似た人たちで満ちていて、そこで成功するか失敗するかは結局運次第といったような、とても過酷な現実が毎日のように突きつけられる」(p.210)のだとしている。これがまさにバーチャルな主体の生のありかたと直結しているのは言うまでもないだろう。こうした現状のさなかで、「サウナ」から「ショート動画」まで、さまざまの癒やしを模索するものの「それでも、どんなに「癒やし」で現状を先送りにしていたとしても〔略〕個別具体的な理由があるわけでは」なく人々が「だがたしかに「死にたい」と思う」(p.213-214)のだとすれば、「バーチャルな主体が環境に過剰に適応するがゆえの「理由はなくとも、自分は死ぬのかもしれないな」といった冷めた感覚。それこそが、なんだかわからないけど死にたくなる幽霊的「死にたい」の正体なのではないだろうか」(p.218)。
僕らは各々個人的な傷や恐れを抱えながら、各自固有な死の約束された生を、いわゆる評判格差社会(橘玲)や評価経済社会(岡田斗司夫)的な競争を強いられつつ生きねばならないので、存在論的な不安を免れ得ないが、一方で、具体的にはどんなものかわからないけどいつか抱えることになるであろう傷や恐れの到来に怯えながら、さっき言ったところのアルゴリズムにも譬えられそうな偶然な死と隣り合わせに生きねばならないバーチャルな主体としては、確率的で郵便的な不安もまた免れ得ない。幽霊的「死にたい」は後者によるものだ。実存的な問題(存在論的な不安)ではないところを根とする限りにおいて、それは自分の内側を探っても出所が見つからない種のものと考えられる。その意味で小川は「郵便的不安から生まれる幽霊的「死にたい」」(p.228-229)を「社会から生まれる社会的な「死にたい」」(p.228)とも表現する。ここで重要かつ厄介なのは、幽霊的「死にたい」を抱える者にはその社会的要因が見えづらく、むしろ見えづらいがゆえに郵便的だったり幽霊的だったりする点だ。
だから小川は、人々の抱え得る「死にたい」への対処のために、敢えて当事者の内面ではなく社会の側へアプローチすることの必要性を述べている。「死にたい」と思うのならば、自分に対してその気持ちを郵便的に齎しているどんな社会的要因があるのか、そういう思考をめぐらせてみる。そうして「社会に「死にたい」をもたらしている構造に対して、予防接種のように処理を済ませ」て「もう自分は、人が確率的に自殺してしまうかのような世界のルールの中で生きてはいない。社会のなかで自殺が起きる道筋から、いまの自分は外れているのだと認識する」(p.227)ことが必要だと言う。「あえて構造的な理路を作り、自分をその理路から剥がすような実感を持つことができれば、幽霊的「死にたい」の声も小さくなっていくかもしれない」(p.311)というわけだ。
そのような理由において、彼はまず「2010年代とはどのような時代だったのか」(p.231)を模索する。そこで得た知見はそのまま僕らが「これから2020年代の日々をどのように生きていくのか」(p.244)を示唆しもする。そしてその意味でこそ、小川は本書で、例えば本稿でも少し触れたように「筋トレをして身体性の変化を探ってみたり」(p.243)、本稿では触れるよゆうがなかったが「ひきこもるように海外移住することで抱えていた困難との関係もいちど断つ」(p.309)という選択肢を提示したり「古今の芸術作品のなかにもその答えを探してみたり」(p.243)していたのだった。あるいは(これも本稿で触れるよゆうはなかったのだけど)ここ最近の宇野常寛がよく言っている「日常×自分の物語がいま、手つかずのフロンティアとして僕たちの前に広がっている」(宇野常寛『遅いインターネット』幻冬舎、2023年、p.131)という地点から問いを深めていたさまも印象深い(余談だが、本書のタイトルにも使われている「日常的」という言葉は宇野の語彙から採用されたのではないかと僕は勝手に想像している)。もちろん安心欲求の言語化もその一環だったと言っていい。そうして小川は「インフルエンスからニュートラリティへ」つまり「アメリカのZ世代の間でしばしばみられるような、社会に押し付けられる理想から離れようとする動き」(p.245)を紹介するのだし、その動きを肯定的に論じながらも「インフルエンサーにはならなくて良いと思っていても、結局は人から羨ましがられたいという欲求に抗えず、日常のリアリティすら承認欲求を満たすための共感の回路として使ってしまう」(p.249)危険を発見し、「今後はいかにして安心欲求のアプローチを純粋に安心欲求に働くためのものとして残すか、機能させるのかという論点が生まれてくるのではないだろうか」(p.250)と指摘するのだった。また、これらのさまざまの問い/提案と同根の文脈で、最後にはフランツ・カフカについて新たな視点を提示するだろう。
かつて小林秀雄は岡潔との対談において「いまの学者は、確信したことなんか一言も書きません。学説は書きますよ、知識は書きますよ、しかし私は人間として、人生をこう渡っているということを書いている学者は実に実にまれなのです。そういうことを当然しなければならない哲学者も、それをしている人がまれなのです」(小林秀雄・岡潔『人間の建設』新潮社、2010年、p.110)と言った。手元の文庫本によるとこの対談の初出は1965年らしいから、もう60年近くも前になるわけだが、しかし引用した箇所の言葉はいまでも有効だ。というより、いまでこそ一層に有効だろう。ここまで『日常的な延命』の内容について身勝手にいろいろ語ってきたけど、最後に言っておきたいのは、僕が本書に感動するのはたんにその内容の良質さだけによるのではないということだ。小川の語りかたの手応え、その実物感、つまり小林が言うところの「学説」や「知識」をおっかなびっくりおどおど連ねて何かを言ったことにしているのではなく、「確信したこと」を張り合いをもって、まさに小川の言う意味での〈アクチュアル〉な筆致で述べているその態度にまず、僕は心を惹かれている。僕がいまこうしてこの文章を書いているのは、書きたいと思わされてしまうのは、たぶんそうした綴りの態度のためなのだと思う。