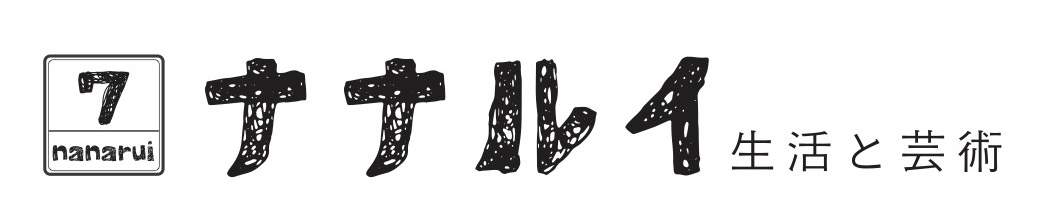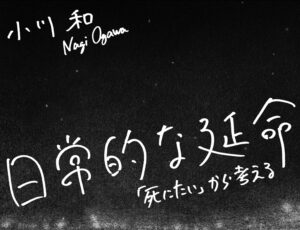金川晋吾写真集「長い間」批評②
「長い間」批評②は、現代美術j家・批評家のNILさんがお届けします
現代美術家・NIL
「間」の倫理とリミナル・ストーリー:他者という閾値に踏み止まること
音の波が移り行く隙間に、瞬間的に存在する静寂。紙の上に描かれた線と線、色彩と背景の境界。二人が座る椅子、テーブルの向こう側に生まれる距離感。文字と文字、行間に広がる空白。身体の動きが交差する瞬間に、無音と同期する呼吸。
「間」と呼ばれるそれは、日常生活のあらゆる時間、空間、言葉、物質、身体、関係性に内在し、沈黙の中に息づいている。同時に「間」を巡る言説や実践はジャンルの壁を越境し、歴史的には枚挙に暇がない。例えば思想史では、和辻哲郎『倫理学』が、間柄と呼ばれる人格という単位では扱うことのできない「間」に対する考察を探求している。またエドワード・ホール『かくれた次元』では、プロクセミックスというコミュニケーションにおける距離(「間」)についての研究が存在する。他方で音楽史では、ジョン・ケージ「4分33秒」が、無音の「間」を音楽作品として前景化した。演劇史においても、サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』は、待つ行為と何も起こらない状態との「間」を主軸に据えた戯曲である。美術史に目を向けると、ブルース・ナウマンの《Corridor Installation》は、鑑賞者が狭い通路を通る体験を通して、「間」の身体的な感覚を強調する。写真史では、アンリ・カルティエ=ブレッソン『決定的瞬間』が、文字通り決定的な瞬間や構図を捉えることで、物語の余白としての「間」を観る者に想像させる。
金川晋吾『長い間』は、日常生活に溶け込みつつも、歴史的な射程を持つ「間」の問題を扱う写真集であることは論をまたない。叔母である静江が消息不明な期間、静江と晋吾の面会時間、写真と日記の日付、被写体と写真と読者の関係性、タイトルと引用文にデボス加工(凹加工)された空白の文字、これらすべてが「間」を象徴する要素だ。本書に焼き付けられた静江の写真イメージと、晋吾が綴る散文日記は、それらを往復する中で無数の「間」を生み出し続ける。しかし、これら多様な「間」の存在を指摘するだけでは、本書の核心に迫ることはできない。なぜなら、本書は長い「間」であるとともに、「長い」間でもあるからだ。では本書において「長い」とは、一体どのような意味を持つのだろうか?
手掛かりの一つとして、伊藤亜紗『手の倫理』に注目してみる。伊藤はまず触覚に関する二つの動詞として、物質的で一方向的な「さわる」と人間的で双方向的な「ふれる」の違いを明確に区別する。その上で「さわる」を基盤とした「まなざしの人間関係」から、「ふれる」を基盤とした「手の人間関係」への倫理の転換を提唱する。ここでいう倫理とは、絶対的に守るべきルールを意味する一般的かつ抽象的な道徳規範とは異なり、迷いや悩みを含んだ正解のない個別的かつ具体的な価値判断のことを指す。
伊藤の提唱する倫理の視点を補助線とすれば、本書に通底するのは「間」の倫理とも呼べる一貫した態度である。晋吾が日記で描写するのは、写真や被写体である静江に対する明確な意味付けや解釈ではなく、むしろ一方的なラベリングを避け、その「間」に踏み止まり続ける思考の流れだ。静江は晋吾の叔母で、元消息不明者かつ認知症の患者であり、生活保護を経た後に自己破産した、などのラベリングの元に写真や静江を認識し、解釈し、理解しようとすることは可能だ。しかし、そのような認識を一旦取り払い、静江という他者との「間」を保ちつつ向き合うこと。「分からないものを、分からないまま」にし、「複雑なものを、複雑なまま」捉えること。晋吾は写真と静江との関係性を通じて、このような「間」の渦中に止まり続ける。それこそが「間」の倫理と称されるべき態度であり、読者はその思考の流れに自然と誘われていく。
伊藤の「手の倫理」も晋吾の「間」の倫理も、ケアや介助の現場から見出されたことは示唆的な事実だ。他方で、これらの倫理における本質的な焦点は、視覚と触覚という感覚の二項対立ではない。むしろ重要なのは、他者との「間」に存在する関係性だ。迷いと悩みを含む「間」を、人間関係の構築や実践、それに伴う倫理の中心として見つめ直す視点こそが、本書が明示するものである。「長い」間という表現は、当然ながら消息不明の期間や面会時間などの時間的な意味を持つ一方で、「間」の倫理を実践するために必要となる空白や余白の「長さ」をも示唆しているのだ。
1978年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された「鏡と窓」展では、キュレーターのジョン・シャーカフスキーが、写真を「鏡」と「窓」の二つの観点で分類して展示した。「鏡」は自己投影、自己表現としての写真を、一方の「窓」は外界描写、社会反映としての写真を象徴していた。しかし、実際にはこの二分法で写真を分類することは困難であり、実態として多くの写真は両者の性質を兼ね備えている。晋吾の取り組みは、この「鏡」と「窓」の二重性、つまり自己と他者、内的体験と外的観察、写真と日記などのあらゆる「間」に、「間」の倫理を持ち込むこととも捉えられる。
私は当初、静江の写真を眺めていた際に、リミナル・スペース(境界空間)とも共通した、不安と安堵が同居する奇妙な感覚を覚えていた。木澤佐登志「Liminal Spaceとは何か」では、リミナル・スペースは二つの異なる場所を結びつける中間地帯として定義されている。この概念は先に述べてきた「間」の問題とも関係するが、両者には決定的に異なる点が存在する。それはリミナル・スペースが無人の場であり、人々の移動を促す人工建造物である点だ。それはアイデンティティの形成や歴史とは切り離された、「非―場所」という概念と密接に関わっている。
写真の静江はイメージとはいえ、人であり、「非―場所」ではない。にも関わらず、両者の感覚が互いに結び付いたのは、静江には背景に存在する物語が極端に少ない、あるいは完全に欠落しているからだろう。静江のポートレートは、「非―物語」としての写真であり、晋吾の日記は静江に対する物語化を阻害し、物語以前の「間」に引き戻す性質を持つ。このような「非―物語」的な他者という閾値を持つ写真と日記の在り方は、リミナル・ストーリーとでも呼べる性質を備えている。それは河原温《Today》シリーズのような、閾値を排した日記の極致ではなく、藤原新也『メメント・モリ』のような、写真と詩による一対一対応の関係性の強化でもない。不安と安堵というアンビバレントな感覚に戸惑いながらも、「間」を保ち続けることを可能にする在り方である。
ロラン・バルト『明るい部屋:写真についての覚書』の一節に、「私がいま見ているのは、ナポレオン皇帝を眺めたその眼である」というものがある。我々が見つめる静江の眼が、過去に何を見てきたのか、その事実は不明だ。それどころかそれは、晋吾の日記を読み進めるほどに、その存在の所在が不確定になるような他者の眼である。静江の眼差しはリミナル・ストーリーとして何かを象徴することに失敗し続け、晋吾の思考は「間」の倫理として認識、解釈、理解の手前で踏み止まり続ける。しかし、そのような静江の変容する眼差しの中に、晋吾の揺れ動く文体の中に、「長い間」が「永い間」へと変貌する可能性を我々は目撃するのである。