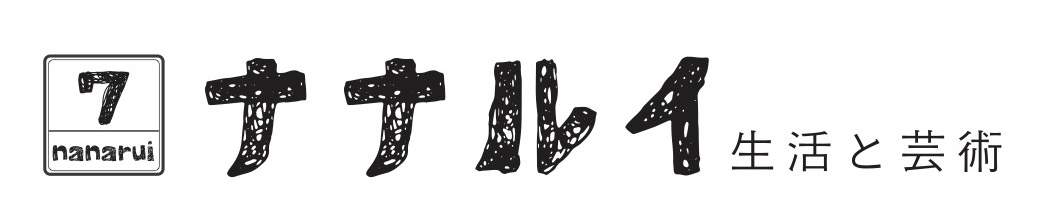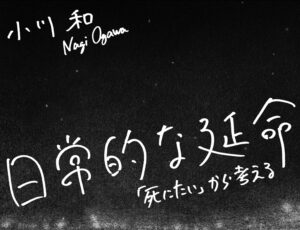『日常的な延命』評① 太田充胤
医師・批評家 太田充胤
『日常的な延命』について、医師で批評家の太田充胤さんに書評を寄せていただきました
日常としての「死にたい」
なによりもまず指摘すべきことは、この本が自殺でも希死念慮でもなく、「死にたい」について書かれた本だということだろう。本書の焦点は、自殺予防でも精神疾患の治療でもない。ふと我々の口をついて出る「死にたい」を、やりすごしたり、飼いならしたりしながら日々を延命することである。実際のところ、それは我々の誰もが多かれ少なかれ経験している、きわめて日常的な所作であるように思う。
20世紀以降、現代科学の発展と宗教の衰退によって、死は人類にとって受け入れがたいものとなった。それまでは共同体のなかで語られ受容されてきた死は、触れづらい話題の一つとなった。とりわけ、死に瀕している人の前で死について話すことははばかられるようになった。1960年代、人類学者のジェフリー・ゴーラー(1905-1985)はこの状況を「死のタブー化」と名づけた。
それから半世紀以上が経ち、状況はずいぶんマシにはなっている。とはいえ、目の前で「死にたい」という言葉が発せられればたじろいでしまうのは現代人も同じだろう。希死念慮をもつ者と接する際には一種の専門性が求められ、それゆえ希死念慮は基本的に親密圏外で吐露されるか、本人のうちに秘められる。希死念慮を抱く者が適切な専門家へとつながるのか、あるいは誰にも知られぬまま実行に至るのか、はたまた「座間九人殺害事件」のように悪魔の手にからめとられてしまうかで、転帰は大きく変わってくる。
さて、しかし、小川の扱う「死にたい」とは、どうやらそういう話ではない。いや、そういう話でもあるのだが、それだけでもないように思われる。というのも、「死にたい」をめぐる思考のために引用される様々な議論は、いずれも自殺や希死念慮そのものについての議論ではないからだ。小川が「死にたい」という言葉で指し示し、思考している対象は、一般に希死念慮という言葉が指し示すものよりもはるかに大きく、一見つかみどころがない。
考えてみれば、今日の一般的な語用において、「死にたい」というつぶやきは必ずしも辞書的な意味においてのみ使われていない。むしろ、単に「辛い」とか「投げ出したい」のような意味で、あるいは「穴があったら入りたい」くらいの他愛ない意味で、カジュアルに使われることも多い。だとすると、希死念慮と「死にたい」、二つの概念の差分には、科学や福祉以前の言葉で考えるべきなにかがある。本書が結果として切り拓いているのは、この領域に関する思考ではなかろうか。
小川は、日々浮かんでは消えるぼんやりとした「死にたい」に、幽霊的「死にたい」という名前をつけて対象化する。一見したところ、幽霊的「死にたい」は明確な希死念慮のかたちをとっておらず、それゆえ実際の死からもずいぶん距離があるように思われる。とはいえ、幽霊的「死にたい」が死へとつながらないわけでもない。カフカが描いたのは、徹底した不作為が餓死を招き(「変身」や「断食芸人」)、理不尽な死刑判決さえおとなしく受け入れさせる(「訴訟」)ということだった。
最低限の生命活動を維持するために、我々はその都度「死にたい」を退ける必要があるのだろう。「生きよう」と強く決意するのではなく、むしろ「死にたい」とつぶやくのと同じくらいの緩さで、「死にたい」を日々保留にし続けるのである。多岐にわたる論客や対象が引用されるのは、彼等がみな「死にたい」という言葉こそ使わないものの、「死にたい」をやりすごすための方法を論じているからだろう。タイトルにもなっている「日常的な延命」という概念には、なにか我々の生の実態を切り出すような鋭さがある。