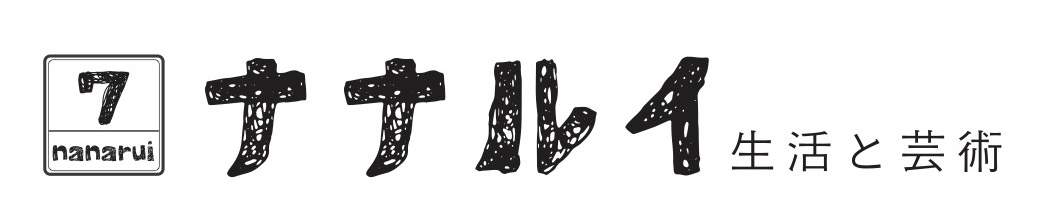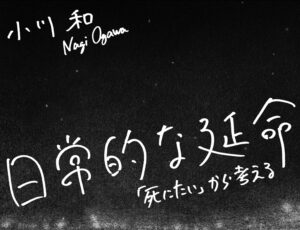『日常的な延命』評② 鎌田裕樹
有機農家・文筆業 鎌田裕樹
『日常的な延命』について、有機農家で文筆家の鎌田裕樹さんに書評を寄せていただきました
延命手段としての「庭」
読み進めるうち、「ああ、こういう感じ?」と、良い意味で裏切られた。
思っていたよりも、ずっと「明るい」本だったからである。
ふと、死にたくなる。
なにか絶望的なことがあったわけでもないし、人間関係にひどくストレスを感じているわけでもない。例えば、原稿の締め切りがあるのに上手く文章が書けないとか、初夏に向けてジャガイモを植えたいのに雨続きで畑が耕せないとか、返すべきメールを溜め込んでしまってどこから手をつけたら良いかわからないとか、ささやかな躓きの積み重ねから、「死にたい」が降って湧いてくることがある。
この本で、著者が掘り下げる「死にたい」とは、「死にたい」そのものだ。この本は「死にたい」の本であって、自殺を扱った本ではない。他者の関心を引くためにSNSに投稿される「死にたい」もあれば、日曜の夜、サザエさんを見ている夕飯時に去来する「死にたい」もある。
第1部では、「承認欲求」という言葉を分解し、「安心欲求」という言葉を用意することで、「死にたい」についての現状把握を進める。著者は、宇野常寛の『遅いインターネット』などの著作や、坂口恭平の取り組み(あるいは、生き方)を引用しながら、安心欲求と「制作」(あるいは、「ひとりあそび」)の関係を書き出す。宇野が説く、「日常×自分」の物語と、坂口が実践する土地に根差したコミュニティ構築を指して、「「庭」のような有機的な環境を整えること」(本文95p第1部安心欲求論 第4章 制作で流れる)の有用性を著者は書いている。
この前後でも何度か用いられている「庭」という喩えが目を引いた。
こんなところに書評(のようなもの)を寄せてはいるが、普段、自分は有機農業を生業とする現場の人間であり、有機的な繋がりを設計するのは、まさしく、我々、農家が取り組むところである。また、庭と農耕の起源は同じだと言われている。(https://hbh.center/04-issue_01/)
雨が降ったあと、春の田んぼからは蛙の大合唱が聞こえる。それらを餌とする鷺が訪れ、隣の竹林ではタケノコが頭を出し、近くの山に数百年前に降った雨水は地下水として里山一帯を潤している。畑で収穫した野菜の屑は鶏の餌にし、鶏の糞は発酵させて肥料として畑に戻す。農業をやっていると、季節の移ろいに敏感になり、有機的循環を目の当たりにする。
「人間は人間以外の事物に触れることで、人間間の相互評価のゲームから一時的に離脱する」― 本文71p「第1部安心欲求論 第3章 安心欲求の摘出」
農業をやっていると、「今、満たされている」と感じる瞬間がある。
自分が種を播き、育てた野菜を収穫するとき。畦のオオイヌノフグリが可愛らしく咲き誇っているのを眺めるとき。蛙の糞のなかにテントウムシダマシ(害虫とされる)の羽を見つけたとき。なんなら、天気が良いとかそんなことにすら安心することがあるくらいで、畑仕事の大半は「人間間の相互評価のゲームから一時的に離脱」している状態にある。農業は、植物を育てることは、「死にたい」に対する「延命」手段だと言えるのではないかと、読みながら考えた。実際、農業とケア、福祉を複合した実践ケースも増えている。
著者は、最初から最後まで、「死にたい」について、「わからない」「わかるわけがない」というスタンスを一貫している。だからこそ、様々な角度から試みられる分析、批評、提言には、一切の押し付けがましさが無い。この本を読んでも前向きにはならないかもしれない。言うなれば、横を向いて、現状を把握し、その場をやり過ごすための本である。それは、逃げることとは違う。あなたの「死にたい」に、今、現在の自分に、あらためて向き合ってみようと、勇気づけられる一冊ではないだろうか。