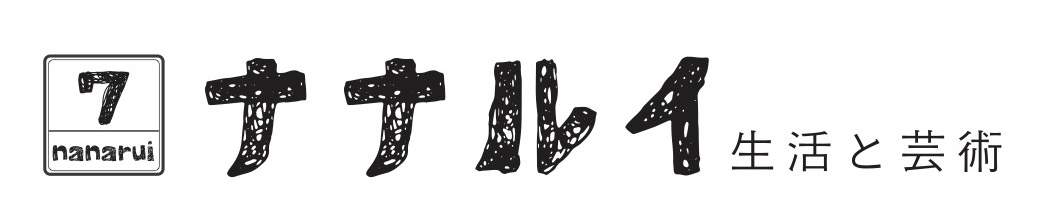『日常的な延命』評 ④佐藤述人
アクチュアルな態度で
無力をばれたくない。無能をばれたくない。なるべく声をひそめて注目されないよう努めたい。注目を浴びたら、それだけ自分の足りなさや異質さがばれるリスクが高まるからだ。なるべく広いところを避けて明るみに出ないよう努めたい。明るみに出されたら、それだけ自分の愚かさや歪さがばれるリスクが高まるからだ。これは同時に、試されたくない、ジャッジされたくないという願望でもある。例えば自信のない分野についての何らかの試験を受けたくないと言うとき、これはたんに出来の悪い試験結果そのものを恐れてそう言う場合もあるにはあろうが、でもそれ以上に、出来の悪い結果が数字や成績として具体的に表れることで、いわば不出来の度合いが明文化され、その分野の自分の苦手さ(足りなさ/愚かさ)がばれるのを避けたいためにそう言う場合も想定できるだろう。試されてジャッジされることは自分の無力や無能が明るみに出されることでもあり、そうなればそこへの注目にも目隠しができなくなるはずだ。続きはこちらから
『日常的な延命』評③やなぎまち
批評に擬態した手紙
ナナルイ」という出版社から、『日常的な延命「死にたい」から考える』という本が出版された。
物心ついたときから「産まれてこなければよかったのにな」という考えに憑りつかれていた私は、早速この本を読んでみた。
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・
『日常的な延命』は、批評に擬態した手紙なのかもしれない。
そこに記されているのは、著者自身によって行われたと思われる延命作業の軌跡である。著者自身があるときに「死にたい」という思いに憑りつかれ、
そこから逃れるべく試してきた様々な経験が、この一冊にまとめられている。
そしてこの本は、手に取った私たちに対して語り掛けてくる。
「僕はこうやって生き延びたけど、あなたはどう?」
とりあえず、その問いかけに対して応えてみようと思う。
まずは、コンスタティブなレベルで。
『日常的な延命』という本は、社会現象、作家、作品などを分析し、その分析を繋ぎ合わせることで、現実世界の問題を言語化し、その問題についての対処方法を著者自身が思考していくことによって進んでいく。
それぞれの思考は、部の単位で分けられながらも緩やかに繋がっていて、部を追っていくごとに思考は絡み合い複雑化する。
各部の表題にはテーマとなるキーワードが提出される。続きはこちらから
『日常的な延命』評②鎌田裕樹
延命手段としての「庭」
読み進めるうち、「ああ、こういう感じ?」と、良い意味で裏切られた。
思っていたよりも、ずっと「明るい」本だったからである。
ふと、死にたくなる。
なにか絶望的なことがあったわけでもないし、人間関係にひどくストレスを感じているわけでもない。例えば、原稿の締め切りがあるのに上手く文章が書けないとか、初夏に向けてジャガイモを植えたいのに雨続きで畑が耕せないとか、返すべきメールを溜め込んでしまってどこから手をつけたら良いかわからないとか、ささやかな躓きの積み重ねから、「死にたい」が降って湧いてくることがある。
この本で、著者が掘り下げる「死にたい」とは、「死にたい」そのものだ。この本は「死にたい」の本であって、自殺を扱った本ではない。他者の関心を引くためにSNSに投稿される「死にたい」もあれば、日曜の夜、サザエさんを見ている夕飯時に去来する「死にたい」もある。続きはこちらから
『日常的な延命』評①太田充胤
日常としての「死にたい」
なによりもまず指摘すべきことは、この本が自殺でも希死念慮でもなく、「死にたい」について書かれた本だということだろう。本書の焦点は、自殺予防でも精神疾患の治療でもない。ふと我々の口をついて出る「死にたい」を、やりすごしたり、飼いならしたりしながら日々を延命することである。実際のところ、それは我々の誰もが多かれ少なかれ経験している、きわめて日常的な所作であるように思う。
20世紀以降、現代科学の発展と宗教の衰退によって、死は人類にとって受け入れがたいものとなった。それまでは共同体のなかで語られ受容されてきた死は、触れづらい話題の一つとなった。とりわけ、死に瀕している人の前で死について話すことははばかられるようになった。1960年代、人類学者のジェフリー・ゴーラー(1905-1985)はこの状況を「死のタブー化」と名づけた。
それから半世紀以上が経ち、状況はずいぶんマシにはなっている。とはいえ、目の前で「死にたい」という言葉が発せられればたじろいでしまうのは現代人も同じだろう。希死念慮をもつ者と接する際には一種の専門性が求められ、それゆえ希死念慮は基本的に親密圏外で吐露されるか、本人のうちに秘められる。希死念慮を抱く者が適切な専門家へとつながるのか、あるいは誰にも知られぬまま実行に至るのか、はたまた「座間九人殺害事件」のように悪魔の手にからめとられてしまうかで、転帰は大きく変わってくる。続きはこちらから
金川晋吾『長い間』批評①きりとりめでる
写真が時間を埋めている。中判カメラは重い。手元に残ったものは何か。
きれいな首だと思った。オレンジ色があざやかなボーダーのトップスは襟ぐりが深いがとても似合っている。肌にあるつつましい粉感は、うすい唇にコーラルオレンジの口紅が引かれていることで、「化粧をしている」という状態に回収されていく。外光につつまれて、顔のしわが眼に入ってこない。真っすぐこちらを見つめている。膝や机の上に置いて、金川晋吾の写真集『長い間』をめくる。バチ、バチっと、金川の伯母にあたる静江と目が合う。静江はたまに張りのないピースを形づくる。静江は今までどんな服を着てきたんだろう。結構スポーティーなものが好みだったのだろうか。真一文字に結ばれた口をみて、写真になる自身の表情、自身の肉とか皺とかといったものの像をコントロールしようとしているんじゃないかなと思った。どの写真の静江も堂々としている。
撮影の為だけでなく、二人のあいだを流れる時間を埋めるものとしても在る写真の束。
たったいま、わたしにこの写真集『長い間』がどう見えているか。
許諾と親密性の可否だけでない他者の撮影の在り方の答えとして現れている。
それを伝えるために、写真というものが現在どういったものなのかを話したい。
2018年のKaoRiによる荒木経惟への告発を受けて、モデルで俳優の水原希子は撮影における被写体の立場の弱さをSNSで綴った1。KaoRiが問題としたのは、荒木が無断で様々な自身の写真を公開したこと、ポーズにしても様々な強要を行ったことだといえる。KaoRiの文章2は、水原の言葉を通して広く理解された。このすばやい理解の素地として、2017年にモデルでタレントのダレノガレ明美がSNSに自身だけ補正した集合写真をアップしたことで炎上したくらいに3、写真を公開するときの、日常的な政治性は議題となっているのだ。続きはこちらから
金川晋吾『長い間』批評②NIL
「間」の倫理とリミナル・ストーリー:他者という閾値に踏み止まること
音の波が移り行く隙間に、瞬間的に存在する静寂。紙の上に描かれた線と線、色彩と背景の境界。二人が座る椅子、テーブルの向こう側に生まれる距離感。文字と文字、行間に広がる空白。身体の動きが交差する瞬間に、無音と同期する呼吸。
「間」と呼ばれるそれは、日常生活のあらゆる時間、空間、言葉、物質、身体、関係性に内在し、沈黙の中に息づいている。同時に「間」を巡る言説や実践はジャンルの壁を越境し、歴史的には枚挙に暇がない。例えば思想史では、和辻哲郎『倫理学』が、間柄と呼ばれる人格という単位では扱うことのできない「間」に対する考察を探求している。またエドワード・ホール『かくれた次元』では、プロクセミックスというコミュニケーションにおける距離(「間」)についての研究が存在する。他方で音楽史では、ジョン・ケージ「4分33秒」が、無音の「間」を音楽作品として前景化した。演劇史においても、サミュエル・ベケット『ゴドーを待ちながら』は、待つ行為と何も起こらない状態との「間」を主軸に据えた戯曲である。美術史に目を向けると、ブルース・ナウマンの《Corridor Installation》は、鑑賞者が狭い通路を通る体験を通して、「間」の身体的な感覚を強調する。写真史では、アンリ・カルティエ=ブレッソン『決定的瞬間』が、文字通り決定的な瞬間や構図を捉えることで、物語の余白としての「間」を観る者に想像させる。続きはこちらから